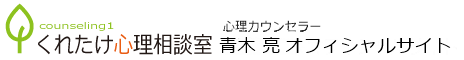裁量労働制の導入時の、カウンセラーからの提言
このブログでは、企業における裁量労働制の導入に当たり、心理カウンセラーとしてコメントさせていただきます。
まずは、裁量労働制の説明を簡単に致します。
裁量労働制とは、労働者が実際に働いた時間ではなく、あらかじめ企業と労働者で定めた時間を働いたものとみなして賃金を支払う制度です。これにより、労働者は自分の裁量で働く時間を決めることができます。
裁量労働制には、以下の2種類があります。
・専門業務型裁量労働制: 特定の専門的な業務に従事する労働者が対象です。例えば、システムエンジニアや研究開発者などが含まれます。
・企画業務型裁量労働制: 企画、立案、調査、分析などの業務に従事する労働者が対象です。例えば、経営企画や営業企画などが含まれます。裁量労働制のメリットは、労働者が自分のペースで働けるため、生産性が向上する可能性があることです。ただし、すべての職種に適用できるわけではなく、導入には労使協定が必要です
労働者は自分のペースで働けることによって、働きやすさや解放感(会社に干渉されない)、責任感から来る充実感などを高く感じやすくなります。労使にとって、WinWinの関係と言えます。
一方で、メリットの裏返しが要注意な点となります。労働者にとっての注意点を以下に4点示します。
- 会社が管理しない、つまり自分が自分を管理する(自己管理)業務が増えます。
- 制度導入前よりも高い成果が求められる傾向があり、ストレスは増えます。
- プロセスと結果の責任の多くが労働者個人に移管され、ストレスは増えます。
- 自己管理に失敗すると、長時間労働や成果未達となるリスクが増えます。
自己管理力と成果、さらにモチベーションの高い方の発言力は一般的に強まり、企業との利害が一致すると導入されやすくなります。しかし、同じ部署で働く方々の中にもさまざまな意見や事情があるのが通常でしょう。順調でないときがあるのは常ですし、そもそも導入時点でそうでない方もおられるでしょう。
つまり、労働者が安定して守られる環境を醸成しておくことが肝要です。そのために以下3点を提言します。
- 自己管理の支援:労働時間や仕事プロセスなどの管理ツールや管理そのものの肩代わり・支援を行う。
- 最低限の時間管理:時間把握を継続し、ラインケアを強化する。過重労働防止は必須で行う。
- 労働者個人の責任軽減:好ましくないプロセスや成果に対して、その責任を個人に求めすぎない態度。
時間管理については、「適度な干渉」が期待されます。労働者にとっても安心感につながりますし、お互いの信頼関係を醸成する機会になりえます。
方略として、上司と部下の”1on1ミーティング”は、たいへん有効だと思います。
また、上司に言えないような場合に備えておく必要もあります。産業カウンセラーなど心理カウンセラーとつながれる環境(内部EAPや外部EAP)は大切だと考えます。
裁量労働制の導入をご検討の企業様におかれましては、ご参考にしていただければ幸いです。
***
私は一企業の労働組合の書記長を経験し、その途中で心理カウンセリングを学び、訓練しました。その後人事に異動し、労組と対峙したり協働したりする担当や、懲戒等の問題事案の対応など広く担いました。(裁量労働制の導入も経験しました。)その後は産業カウンセラーとしての学びも加え、それらを通した見識を、適宜お伝えさせていただきたいと思います。
企業と社員がともに、幸せなプロセスと成果を得られるようなご支援を、心理カウンセリングを含むメンタルヘルス支援など、微力ながらさせていただきます。どうぞご相談ください。
投稿者プロフィール

- くれたけ心理相談室(名古屋本部)心理カウンセラー 産業カウンセラー
-
こんにちは。広い空や海の開放感が大好きなものですから、
自分への日々のご褒美には、広い空間の体感かスイーツやお酒少々です。
皆さんの明日が今日よりも、明後日が明日よりもステキでありますように。
最新の記事
 こころおだやか2026年1月8日凛とした空気に心整う
こころおだやか2026年1月8日凛とした空気に心整う こころの理2026年1月7日「底力」という安心感
こころの理2026年1月7日「底力」という安心感 カウンセリング2026年1月6日結婚する前に気づきたい
カウンセリング2026年1月6日結婚する前に気づきたい ご高齢の方へ2026年1月5日老いた親の「自分でやる」
ご高齢の方へ2026年1月5日老いた親の「自分でやる」